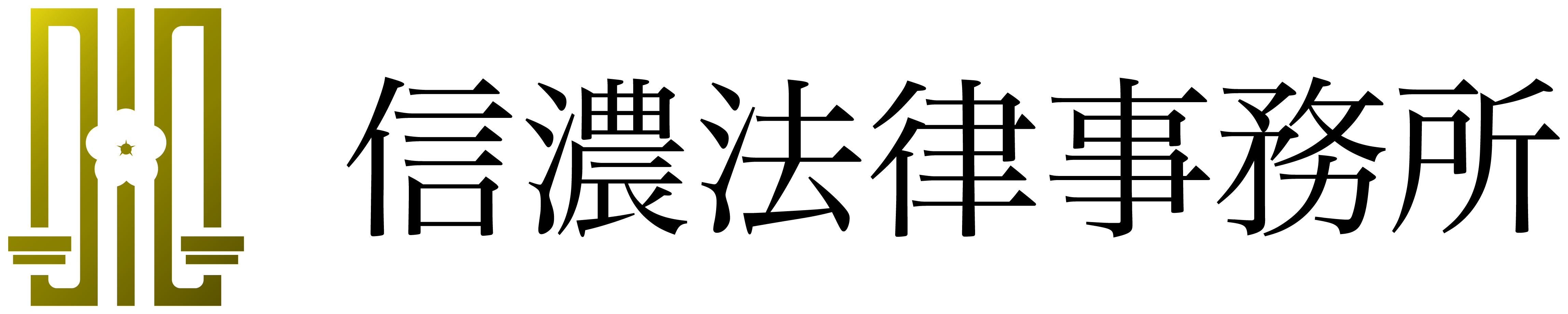「見落とされた癌」は、ボクシング元ミドル級世界チャンピオンの竹原慎二さんが膀胱がんの闘病生活を描いたものです。
公私ともに親しくしていたかかりつけの医者であるA医師のミスで癌の発見が遅れたとの思いが本の題名になっています。
A医師は、頻尿や排尿痛を膀胱炎、前立腺炎、前立腺肥大と診断し、血尿が出たところで、総合病院の泌尿器科(B医師)を紹介します。
紹介され検査をしたB医師は尿細胞診の結果を、検査から1ヶ月後、竹原さんが2度目の大量血尿で病院を訪れたところで慌てて検査結果を確認して「癌」と診断します。
その後、いったんはB医師の病院で入院手術をすることに決めましたが、「こちらも命がかかっているので妥協はできない。そちらの病院に命を預けるわけにはいかない。だから転院を決めた」と、入院前日、予約をキャンセルし東大病院へと転院します。大事なことは、竹原さん自身が信頼できる医師のもとで納得いく治療を行ったということでしょう。
治療方針は抗がん剤、GC治療です。
GC治療とは手術を前提とした抗がん剤治療です。
抗がん剤は髪が抜ける等の副作用があったものの効果がありました。
手術は膀胱を摘出して小腸を切り取り、小腸で新膀胱を作るという方法です。
膀胱の全摘出と新膀胱設置の手術は無事成功しました。
その後の病理検査で骨盤のリンパ節へ2か所転移していたがんがすべて消えていることが分かりました。
退院後はさらに免疫治療も行うという徹底ぶりです。
そして、免疫治療も予定されたものが全て終了したその日、奥様が件のA医師に抗議の電話をします。
それまでもずっと抗議したかったのを、夫の治療に専念するため、ずっと押し殺していたのです。予定された治療が全て終了したその日に、奥様はA医師にすぐに電話して、同医師への怒りを、竹原さんの思いを代弁して、全てぶつけました。
竹原さんとしては、自分の怒りの気持ちを、奥様が自分以上に怒って相手にぶつけてくれた、こんなに嬉しいことはなかったのではないでしょうか。
私はこのシーンが一番印象に残っています。
竹原さんは、治療終了から約3年後にA医師らを被告として損害賠償請求の訴えを提起します。
判決では、竹原さんがA医師の誤診を問題とした期間(平成24年2月~25年8月)に、竹原さんが長期間(最大で約9カ月)通院していない時期があったことをもって、症状は軽快した、治癒したと捉え、
その後、尿検査、尿沈渣の検査が行われたが、(特に最後の検査で)赤血球等の数値がそこまで悪くなかったことなどを理由に、
膀胱がんを疑うべき所見があったとは認め難いとして、A医師の過失(泌尿器科専門医への転医ないし同専門医の受診を指示すべき注意義務)は認められませんでした。
竹原さんがA医師を受診していなかった時期が約9カ月あったことが判決の大きな理由となったと思われますが、問題はいつ膀胱がんを発症したかであり、判決はこの視点が抜けています。
本書や判決文を読む限りは
平成24年2月からの一連の症状には同質性があるように思われ、
そうだとすると、膀胱がんの進行速度にもよりますが(一般に概ね早期がんは「年単位で進行」、進行がんは「半年単位で進行」、末期がんは「月単位で進行」すると考えられています)、
平成26年3月頃にはステージ4だったということも考えると、平成24年2月頃から既に膀胱がんを発症していたのではないかと考えられます。
通院していない時期が数カ月あったからといって、膀胱がんが治療もなく軽快(治癒)したというのはおよそあり得ないでしょう。
竹原さんとA医師は、ただの患者ではなく、公私ともに親交があったとのことですから、クリニックに通院していないとしても、症状を訴えていたということは考えられるでしょう。
また、積極的に膀胱がんを疑わせる所見がなかったとしても、A医師は泌尿器科医ではないのですから、症状の原因が分からず、重篤な病気の可能性を否定できない状況であれば、早期に専門医に、高次医療機関に引き継ぐべきであったと言えるのではないでしょうか。
竹原慎二さんについてはあまり知らなかったのですが、本書を読んで好感を持ちました。同じ病気(膀胱癌)の人でなくとも参考になる所が沢山ある本です。
竹原さんに限らず、「見落とされた〇〇」というケースは多数あります。
本来ならもっと早期に発見できたのではないか、仮に早期に発見できたとして予後はどうだったのか、これを究明するのが医療過誤訴訟です。
弁護士 臼井義幸